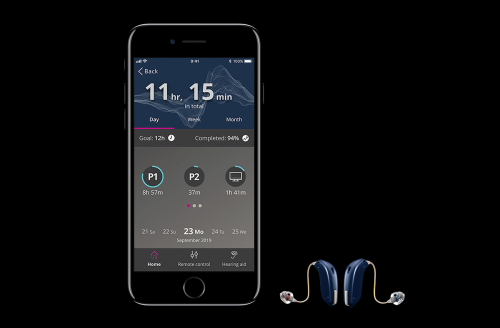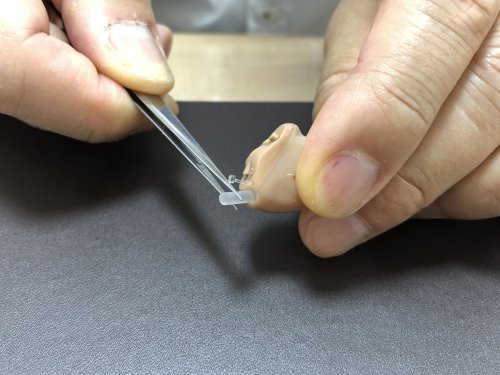補聴器 マスク生活での補聴器選び
- 2021/02/20 12:29
- カテゴリー:補聴器
補聴器が初めのお客様で、耳かけ型補聴器を試されていますが、
今はコロナ禍でマスクを着け さらにメガネも掛けているので、
耳あな型補聴器をご注文いただきました。
上の写真のように
耳かけ型補聴器は、マスクを外す時に補聴器が絡まり落ちそうになります。
耳あな型補聴器だと、本体が耳のあなに収まり
マスクやメガネの邪魔になりにくいです。
コロナ禍でまだまだマスクは手放せないので、
耳かけ型・耳あな型補聴器の落下防止用チェーンなどのグッズもあります。
片耳用 ¥3,000~ (税別)
両耳用 ¥3,400~ (税別)








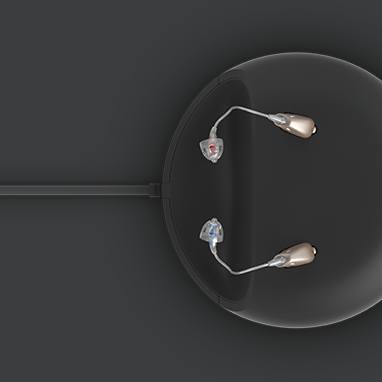 充電器のケーブルを電源に接続します。
充電器のケーブルを電源に接続します。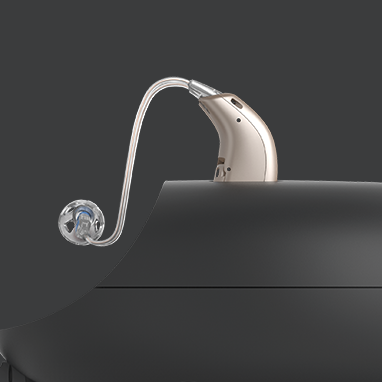 簡単にセットいただけます。
簡単にセットいただけます。 非接触充電技術を採用
非接触充電技術を採用